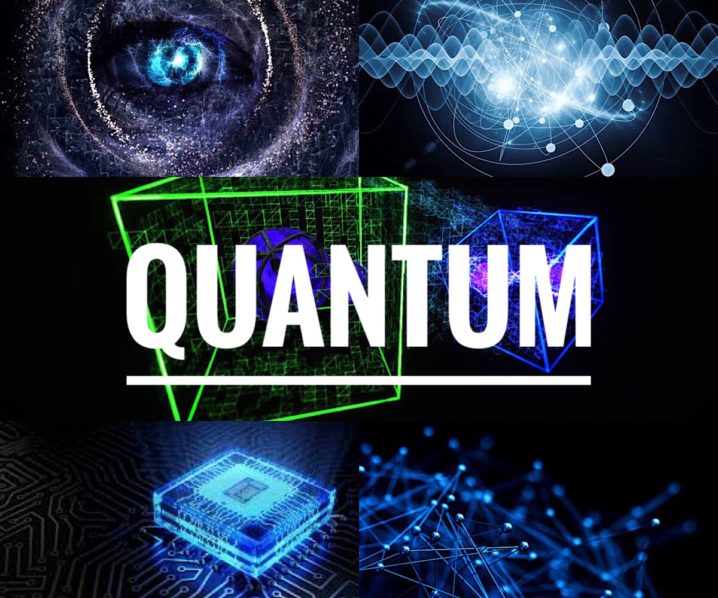「5G」:第5世代移動通信システムが動きだした。AI/IoT/VR/AR
量子コンピューターとは

従来のコンピューターは、0と1の信号(ビット)でカウント(足し算)を行って計算をする仕組みです。
パソコン用のCPUであれば、コア数に応じて計算します。4コアのCPUであれば、同時に4つの計算ができることになります。量子コンピューターは、量子の重ね合わせによって非常に多くの並列計算が可能になります。
従来の技術ではコア数で数の並列計算しかできなかったようだけど、量子コンピューターであれば膨大な数の並列計算ができるみたいです。
この技術を応用すれば、パスワードを解読することも一瞬です。
例えば0~9の数字から4桁の暗証番号を見つける場合、現在の技術では順番に0000から9999まで1万通りの数字を1つずつ入力して試さなければなりません。
量子コンピューターであれば同時に1万個の数字を入力して試すことが可能なので、最も簡単にパスワードの解読ができてしまう相当ヤバイやつです。
量子コンピューターの仕組み・原理

現在使用されているコンピューターはスイッチを切り替えて数千個の電子が移動させて、0と1のビットを識別させる仕組みらしいです。
大量の電子を移動させると、各ビットの状態は0か1のいずれかに確定されます。これに対して量子コンピューターでは、1個の素粒子だけで0と1を表現します。
素粒子は2つの状態(スピン)を持つので、スピンの向きによって0と1の信号を表現することが可能とのこと。量子のスピンとは、磁石のN極とS極のようなものだと考えると分かりやすいと思います。
※量子論(不確定性原理)によると、素粒子の状態(スピン)は同時に2つの状態を作り出すことが可能
量子の性質を応用すれば1つの素粒子を用いて同時に2つの計算ができることになるので、組み合わせの数が多い計算でも尋常じゃない早さで答えがわかります。
・現在のコンピューター
暗号の解読や多くのパターンの中から1つだけ正しい答を見つけるなどの課題を与えると、順番に計算をしなければならないので指数関数的に計算量が増えてしまいます。
・量子コンピューター
膨大な組み合わせの状態を同時に作り出して1度に計算をしてくれるので、従来のコンピューターで時間がかかり過ぎていたような計算も短時間で答えを得ることが可能になります。
量子コンピューター「得意な事・不得意な事」
■量子コンピューターが得意な事
膨大な組み合わせがあるようなパズルを短時間で仕上げるとか、最適なルートや方法を1つだけ発見するといったことが得意です。膨大な組み合わせの中から1つだけ答えを見つける場合のように、既存のコンピューターでは計算量が多すぎて計算が不可能だったことが可能になります。
■量子コンピューター不得意な事
動画・音声データの変換や1つ前の結果を利用して段階的に計算をさせて次々に答えを求めさせるような課題は、既存のコンピューターの方が得意とのこと。
3Dゲームでは、順番に座標を変換することで仮想空間を移動するような画像を描きます。これは1つ前の「風景」のデータを使用して座標変換をしてから次の風景の画像を描く、といった作業の繰り返しです。
最初からプレイヤーの動きを完璧に予測することは不可能なので、ゲームのプログラムは既存のコンピューターの方が得意らしく、量子コンピューターが実用化されると従来は不可能であった計算ができるようになりますが、従来型のコンピューターが不要になる訳ではありません。
量子コンピューター実用化に向けて

現在は、世界中で量子コンピュータの実用化に向けて研究が進められています。
量子コンピュータは1個の量子(電子や光子)の状態を読み取ったりスピンを制御する必要があり、これにはかなりの技術力が求必要らしいです。
計算を行うための量子チップを絶対零度(-273℃)付近まで冷却して、微小な量子のスピンを正確に読み取るための装置が必要らしく、実用化のためにはチップを冷却させたり量子のスピンを制御して読み込ませるための装置を開発しなければなりません。
現状の技術では、非常に大がかりな装置になってしまいます。
現状では極低温に冷却するための装置が必要で、データを読み取る際にエラーが頻繁に発生するといった問題があるようです。非常に多くの課題をクリアしなければならないので、商用に実用化されるのはまだ先のことになりそうです。
『量子コンピューターの実用化のためには、ハード面だけでなくてソフト面の開発も必要』
量子コンピューターの能力を発揮させるためには、専用のアルゴリズムを開発してプログラムを作らなければならないようで、従来型の計算機とは全く違うプログラミング技術が必要とされるようです。
量子コンピューターに対応するGoogleとMicrosoft各社状況
世界中で量子コンピュータの開発競争が行われていますが、特に力を入れているのが毎度お馴染みのGoogleとMicrosoftです。
Google社によると、実用化のための条件として49量子ビットかつ量子回路の深さが40以上必要で、量子ビット間の量子ゲートのエラー率を0.5%以下にする必要があるとしています。
この目標に近づかせるためにチップの開発が進められて、インテル社が49量子ビットのチップの開発に成功しました。
ただし量子エラー率が0.5%を越えているため、実用化のためには更なる改良が求められているようです。
エラー率を低く抑えることにより、少ない量子ビットで済むというメリットがあります。
マイクロソフト社はハードウェア(チップ)の開発を進めながら、ソフトウェアの開発も行っていて、2017年9月末に法人向けに開催されたイベントで、マイクロソフト社は量子コンピューター向けに開発した新しいプログラミング言語を公開することを発表しました。
量子の世界を調べていくと最終的に人間とは?に行きついてしまいました。
その答えも じきにわかるのかも?
[wpap service=”with” type=”detail” id=”4798157465″ title=”絵で見てわかる量子コンピュータの仕組み”]